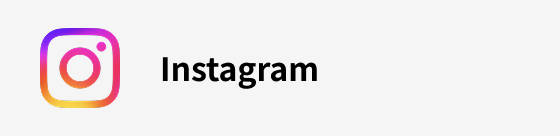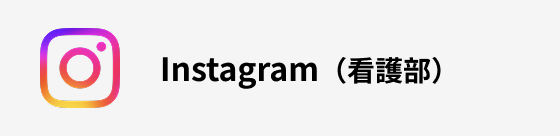診療科・部門

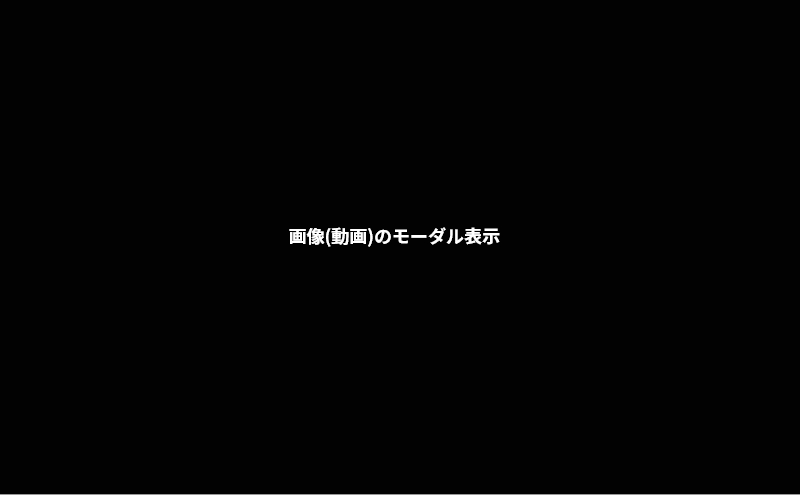
リハビリテーション部

スタッフ
当部は令和5年10月現在、リハビリテーション部長(整形外科主任診療部長兼任)以下、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床心理士、事務補助員で組織されています。
業務内容
理学療法・作業療法・言語療法
医学的リハビリテーションのうち、理学療法サービス、作業療法サービス、言語聴覚療法サービスを提供しています。
当部の特色は、機能障害(Impairment)に対する治療にあります。リハビリテーションの観点に立てば、能力障害・社会的不利への対策は重要で、在宅生活・療養生活を見据える必要があります。しかしそれ以前に、急性期病院の位置づけとして「機能障害をいかに速やかに回復・軽減させ、次につなげるか」が当部の役割として重要と考えています。そのため疾患の病態や病型に応じ、発症早期からのリハビリテーションを開始(下図「急性期医療への関わり」参照)し、生じうる障害や合併症を可能な限り予測し、それらを最小化させていく必要があります。また近年は、身体運動機能障害のみではなく様々な内科的疾患や精神面の問題も合併されている方も増えてきており、多職種によるカンファレンス等を行い、これらに対応した療法も行っています。
患者さんの回復状況に合わせ、医療連携センターを窓口とした病院連携・病診連携への参画、医学的リハビリテーションに留まらず、在宅・就労・就学生活再構築のために院内外の関係者・関係機関との連携も必要に応じ行っています。
急性期医療への関わり(ICU・救急病棟実績)
- 年度別実施患者数(人)
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 言語聴覚療法 648 816 1433 1351 1372 作業療法 32 327 564 824 1036 理学療法 1430 2509 3981 3917 3459 - 年度別実施単位数(単位)
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 言語聴覚療法 859 1105 2089 1974 1969 作業療法 38 477 871 1265 1468 理学療法 2695 4396 6285 6159 6193
広報物
- 2021年5月、医療機関向け医療コラム「MINATO COLUMN」(みなとコラム)「集中治療後症候群(PICS)~ICU入室から社会復帰を見据えた取り組み~」を発行しました。以下をクリックすると、紙面をご覧いただけます。
- 2022年12月に発行した患者さん向け広報誌「みんなのみなと」2号にて、「今でも元気づけられる『ありがとう』のお返し」という題で、作業療法士の取り組みについて掲載しました。以下をクリックすると、紙面をご覧いただけます。
- 2022年4月に発行した患者さん向け広報誌「みんなのみなと」4号にて、「こころの健康」について掲載しました。以下をクリックすると、紙面をご覧いただけます。
- 2022年9月に発行した患者さん向け広報誌「みんなのみなと」6号にて、「ロコモティブシンドローム」について掲載しました。以下をクリックすると、紙面をご覧いただけます。
理学療法



理学療法サービスは、疾患別リハビリテーション(運動器、脳血管、呼吸器、心大血管、がん患者リハビリテーション、廃用症候群)に対応したチーム制とし、早期社会復帰を最終目標として理学療法を行っています。
疾病または障害発症から早期、あるいは手術前から理学療法を開始することで、二次的な廃用症候群や機能障害の低減をはかっています。より早く介入することで身体の運動機能の状態を整え、生活の再構築のための基盤作りを目指しています。
当院理学療法サービスの特徴
- 早期理学療法開始による身体的機能障害の低減をはかる。
- 術前理学療法による二次的機能障害の予防・低減につとめる。
- クリニカルパスの活用による、安全・計画的な理学療法の提供。
- がん患者に対するリハビリテーションの提供。
- 小児発達遅延や障がい(児)の方およびご家族に対し、発達相談および理学療法の提供。
作業療法



作業療法は「そのひとらしい生活が送れるようになること」、「そのひとにとって大事な作業(日常生活動作をはじめ、仕事や役割、趣味活動などの生活行為)ができるようになること」を目指して、様々な作業を手段として、または目的として行います。
治療が優先され、さまざまなデバイス類に囲まれる急性期医療の中での作業療法は、回復期や維持期とは一見違うように見えるかもしれませんが、根本の理念やベクトルの方向は同じです。異なるのは突然の疾病や障害によって身体面だけでなく、精神・心理面、とりまく環境が大きくかわることです。
当院の作業療法部門で力を入れているのは、「超急性期からの精神心理面への支援」と、「認知症やせん妄のある患者さんへ集団活動提供」です。
超急性期からの精神・心理面への支援
昨今、ICUやHCUなど特殊な治療環境の中でいわゆる集中治療後症候群(PICS)と呼ばれる心身の機能障害を起こすことが知られています。超早期からリハビリテーションを行うことが推奨されており、リハビリテーション部でも病棟スタッフと協力して、理学療法士、作業療法士が対応にあたっています。作業療法士は積極的な離床やADL拡大に関わると同時に、ICU退室後のPTSDなどを軽減する目的で、患者さんの日常を綴った「ICUダイアリー」を作成し提供しています。また、一般病棟でも精神・心理面のフォローアップを目的とした小集団活動を行っています。
認知症やせん妄のある患者さんへの集団活動提供
入院患者さんが年々高齢化してきており、認知機能が低下した患者さんの中には入院後混乱や錯乱を伴う「せん妄」を来す方が少なくありません。せん妄によって治療やリハビリテーションが進まなくなることがあるため、認知症サポートチーム(DST)と協働で生活リズムを保ち、安心できる時間と空間を提供する「院内デイケア」を行っています。
言語聴覚療法



言語聴覚士は「話す」「聞く」「食べる」のスペシャリストです。
言語聴覚士は病気や事故、発達上の問題などでことばによるコミュニケーションの機能や食べる機能に問題が生じている方に対し、専門的サービスを提供し、その人らしい生活が構築できるように支援します。
当院言語聴覚療法について
- 当院に入院されている脳血管疾患や呼吸器疾患、がん患者などの方のコミュニケーション機能や食べる機能の問題に対して、必要に応じて超急性期から関わっています。
- 外来では子どものことばの発達の遅れ、発音がはっきりしない、コミュニケーションが取りにくいなど、ことばに関する心配や、食べる機能に関して困りごとがあるお子さまに対して専門的サービスを提供しています。
- その他に耳鼻咽喉科の外来診療の補助として各種聴力検査や、成人の人工内耳のフィッティングも行っております。
視能訓練


視能訓練士とは、主に「視能矯正」「視能検査」「健診/検診」「ロービジョンケア」を業務とする視能検査と視能矯正の専門家です。斜視・弱視の視能訓練という専門分野のみでなく、眼科一般分野での幅広い視能検査へと業務分野は拡大しています。人間の一生に関わる「目」の健康管理。視能訓練士は眼科領域における専門技術者として、乳幼児からお年寄りまで大切な目の健康を守るお手伝いをしています。
当院における視能訓練士業務について
- 眼科一般分野の視能検査
視力や眼圧などの測定から白内障をはじめとした手術のための検査や、眼底造影検査まで幅広く行っています。総合病院のため全身疾患をもつ患者さんも多く、緑内障だけでなく頭蓋内疾患への視野検査、外傷や甲状腺眼症への眼位・眼球運動検査も多く行っています。他科の診断・治療方針決定にも関わるため迅速で正確な検査を心がけるとともに、見やすくわかりやすい検査結果も意識しています。 - 眼科専門分野の視能訓練
弱視・斜視の患者さんの両眼視機能を回復させるための視能検査及び視能訓練。
弱視:屈折矯正、弱視訓練
斜視:屈折矯正、眼球運動訓練、プリズム処方 - 健診・検診業務
心理療法

心理療法とは、主に対話を通して精神的な不調をおこしている方の思考や行動、感情に働きかけ、自己受容を促していく過程のことを言います。主に下記のようなアプローチ方法があります。
- 来談者中心療法
- 精神分析
- 認知行動療法
- 行動療法
- 交流分析
当院の臨床心理士の業務
- 入院患者さんのこころのケア
- 外来患者さんのカウンセリング業務
- 認知、発達などの心理検査業務
- 緩和ケアチームの心理的ケア
- 心療内科・精神科へのリエゾン対応